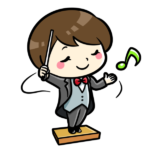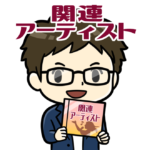当ブログ管理人は「この曲ヤバイ!なんかイイ!」から卒業できるのか?
TOKYO GAME SHOW 2020 スクエアエニックス
こちらの企画はTGS2020のオンライン動画企画として2020年9月25日に放送されたものになります。
「音楽の良さを言語化するには?」というテーマの元、FFの複数の楽曲を取り上げ、評論家やピアニストを交え話を進めていくという素晴らしい企画でした。
目次
私のための企画疑惑
この企画を目にしたときの私の率直な感想としましては、「えっ?自分のためにあるような企画じゃない!?」でした。
しかも、取り上げた楽曲が私の特に思い入れの強いFF9、FF10ということで、怖いくらいに私にマッチングしております。
とはいえ、スクエニさんがこの辺境のブログに辿り着けるわけがないので、「偶然とは凄いな」としか言いようがありません。
好きなFF作品が被った高橋愛さんとは「気が合いそうだな」なんて思いつつも、この辺境のブログに辿り着……
出演者
既に名前を出してしまった方もいらっしゃいますが、ここでご紹介させて頂きます。
MCはゲーム好き芸人のヤマグチクエストさんが担っております。
元モーニング娘。の高橋愛さんは「FFファン」という立ち位置で、ご自身の好きな楽曲を紹介しつつ、その感想を言葉にしてみるという役割を担っています。
音楽評論家、詩人という肩書の小沼純一さんは、高橋さんの感想に助言するというのが主な役割なのですが、視聴者に向けて多くの知識を教えて下さる先生的な役割でもあります。
ゲーム音楽にも精通されているピアニストのかてぃんさんは、鍵盤の音を出しながら、小沼さんの解説を視聴者が実際に耳で聴いて分かるよう補足する役割をされています。
いわばタブル解説のような布陣なのですが、とにかくこのお二人のお話には非常に勉強させられました。
私自身何度聴いたかわからないくらいの楽曲でも専門的な意見が入ると、楽曲の印象が変化するような感覚がありました。
紹介された楽曲
さて、今回の企画で紹介された楽曲ですが、以下のようになっております。
FF9より
1.いつか帰るところ
2.クジャのテーマ
3.古根の道ガルガン・ルー
FF10より
1.シーモアの野望
2.ビサイド島
3.ザナルカンドにて
4.祈りの歌
それぞれのオープニング曲は有名どころですが、なかなか通好みだなと思わせる楽曲も含まれています。
「ビサイド島」のみ浜渦正志さんの楽曲で、他は植松伸夫さんの楽曲です。
高橋愛さんにとっては敵対するキャラクターが印象深くなり易い傾向があるのか、クジャとシーモアの両方を取り上げてしまったのはちょっと勿体なく感じました。
敵対キャラクターの楽曲という共通点がある中で、それぞれにどのような工夫が詰まっているのかと考えると興味深いところではあります。
しかし、植松さんの人間味のある楽曲をどのような言葉で表現されるのかが気になったので、どちらかはパーティキャラクターの楽曲にした方が嬉しかったかなとは思いました。
さて早速ではありますが、各楽曲の解説から私が学び取ったことをまとめていこうと思います。
学んだこと
いつか帰るところ
まず、小沼さんがおっしゃった「長調でも単調でもない」という発言ですが、こちらは音楽の基本知識によるところではあります。
長調とはメジャースケール、単調とはマイナースケールで構成された旋律ということなのですが、私がゲーム音楽を聴くにあたってこの辺りを意識したことは驚く程にありませんでした。
なので小沼さんが「どっち?」と質問されたときはドキっとしました。
分からなかったというのもそうなのですが、何より基本知識のところがゴッソリ抜け落ちている自分に気付いてしまったのです。
生憎、我が家には鍵盤楽器が無いのですが、ギターはありますので、今一度スケールを奏でることでその辺りを感じ取ろうと思いました。
もう1つは「長調でも単調でもない」、「コード(伴奏)がない」といった特徴から、小沼さんが音楽史的な視点でのお話をして下さったのが印象的でした。
ゲーム音楽といえば数多の音楽ジャンルから構成されていますが、こうした歴史的な知識や、ジャンルの特徴といったものを知っていれば、楽曲の特徴を言語化するのに大いに役立つなと感じたのです。
自分の中に漠然とあった「知識不足」というのはこういったことなんだろうなというのが具体的に見えてきたような思いがしました。
クジャのテーマ
ここではかてぃんさんが仰っていた転調の話が印象的でした。
転調について個人的なイメージとしてあるのは、終盤に楽曲を盛り上げるための役割があるというものだけでした。
しかし、かてぃんさんは楽曲を落ち着かせるという使用方法もあると仰っており、その辺り具体的に感じられるよう様々な楽曲を意識して聴いてみようと思いました。
また、「クジャのテーマ」では更に別の役割があるということで、興味深かったです。
ただし、聴いてもなかなか「ここが転調だ」とは私には分からないことも多いだろうなと思うので、この辺は意識しながら聴いてみる他ないのかなと思いました。
古根の道ガルガン・ルー
ここではやはり楽曲のループに纏わるお話が興味深かったです。
特に、かてぃんさんの仰っていた「ループして元に戻れるというのはゲーム音楽の特徴だが、始まりも曖昧で何処から聴き始めても自然になるようにつくられている」というお話が興味深かったです。
サントラではループせずに終わるパターンと、2ループ程度収録しているパターンとありますが、そのループの有無でも楽曲の印象って少し違うよななんて思いました。
繰り返されることで、その楽曲が自身の中にうまく定着してくるという感覚があるなと思いました。
シーモアの野望
「ゲームの映像はまだ人の演じているような複雑な表情とかはまだ出ないのだけれど、どういうものを音楽が作っている」という小沼さんのお話が印象的でした。
ゲームグラフィックって向上していますが、確かにまだそこまでは辿り着けていないかもしれないと今更ながら気付いたのもそうですし、だからこそまだまだ音楽の入って行く余地はあるなと感じたのです。
もちろん場面にもよるのですが、環境音楽化はまだ早急なケースもあるように思いました。
この楽曲については音の重なりでシーモアを表現しているという話になっていましたが、「どのように表情をつけているのか」という部分に着目して言葉にするのがゲーム音楽を語る上で重要なことであると感じました。
ビサイド島
この楽曲ではヤマグチクエストさんのビサイド島のイメージとして「自然豊かでカラフル」という表現をしていたのですが、私はこの「カラフル」の部分が盲点になっていたなと感じました。
言われてみればたしかに、水や空、木々の色なんかが相まってカラフルな印象があります。
こうして他の人のイメージを聞くことで「確かに!」となることは多いのだろうなと感じました。
小沼さんのゲーセンのUFOキャッチャーの音の話から、「人がどう反応するかって、いかに違うかっていう例です」というお話をされたのも、自分には想像もつかないような捉え方があるのだなと感じ、なかなか面白いなと思いました。
ザナルカンドにて
ここはカティンさんのピアノの特性についてのお話が勉強になりました。
ピアノの特性として、「音が減衰する、1音の抑揚ができない」というものがあり、それによって心内を表現し易いといったものがあるというお話でした。
私が持っていたピアノの特性のイメージは「押すだけで音が鳴るため、より複雑に多くの音を用いた表現ができる」というものだったのですが、かてぃんさんのお話でピアノについてのイメージの幅が広がりました。
特性を意識しながら様々なピアノ楽曲を聴いてみようと思いました。
祈りの歌
小沼さんの仰っていた「瞬間瞬間の和音の響きがよく考えられている」という話があったのですが、そういえば私も最近ゲーム音楽における「和音」を意識する場面が多かったなと思いました。
和音は音楽的な美しさが強く出る部分だと思うので、今後も美しい和音を見付けたら、遠慮なく言葉にしていこうと思いました。
まとめ
放送では7曲も紹介され、時間も訳60分短くなかったのです。
しかし、それでもこの方たちがゲーム音楽の楽曲についてどう言語化するのか、もっともっと聞きたいと思いました。
それだけ、楽曲に対する言葉が豊富だったということだと思います。
そして、そこは私自身にシンプルに足りない部分であり、当ブログの読者が「この人のゲーム音楽の話をもっと読みたい」となっていない現実が生々しく突き刺さってくる感覚もありました。
読者が少ないのは多くの理由がありますが、その1つとして「もっと読みたい」という感想に至らない私自身の言語化の質の低さがあるのだと思います。
そこは、もうとにかく聴いて書いての繰り返しで成長していくしかないのですが、今回の放送は非常に役立った部分があったと思います。
また、最後に小沼さんから大変印象的な言葉がありました。
「自分だけで閉じない、話していくからこそ、もっと上に行ける」
そもそも私自身の言語化が未熟なせいで「話していくこと」すらできていないのかもしれません。
まずはゲーム音楽の何が良いと思っているのか、しっかりと話していくこと。
それを受けた方の反応があれば、そこで自分の感覚がさらに成熟していくのかもしれませんが、まずは話していくことができるように知識や言葉を磨いていこうと思いました。